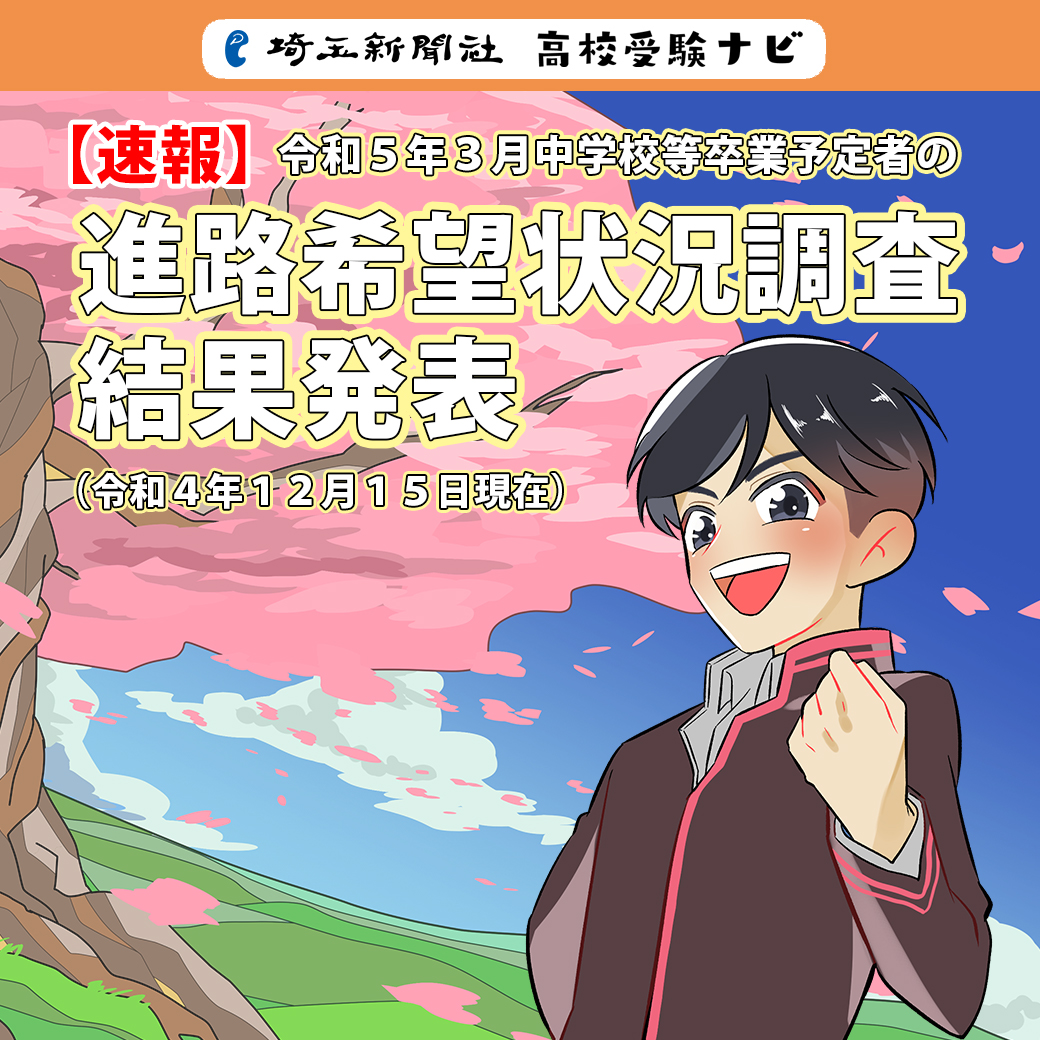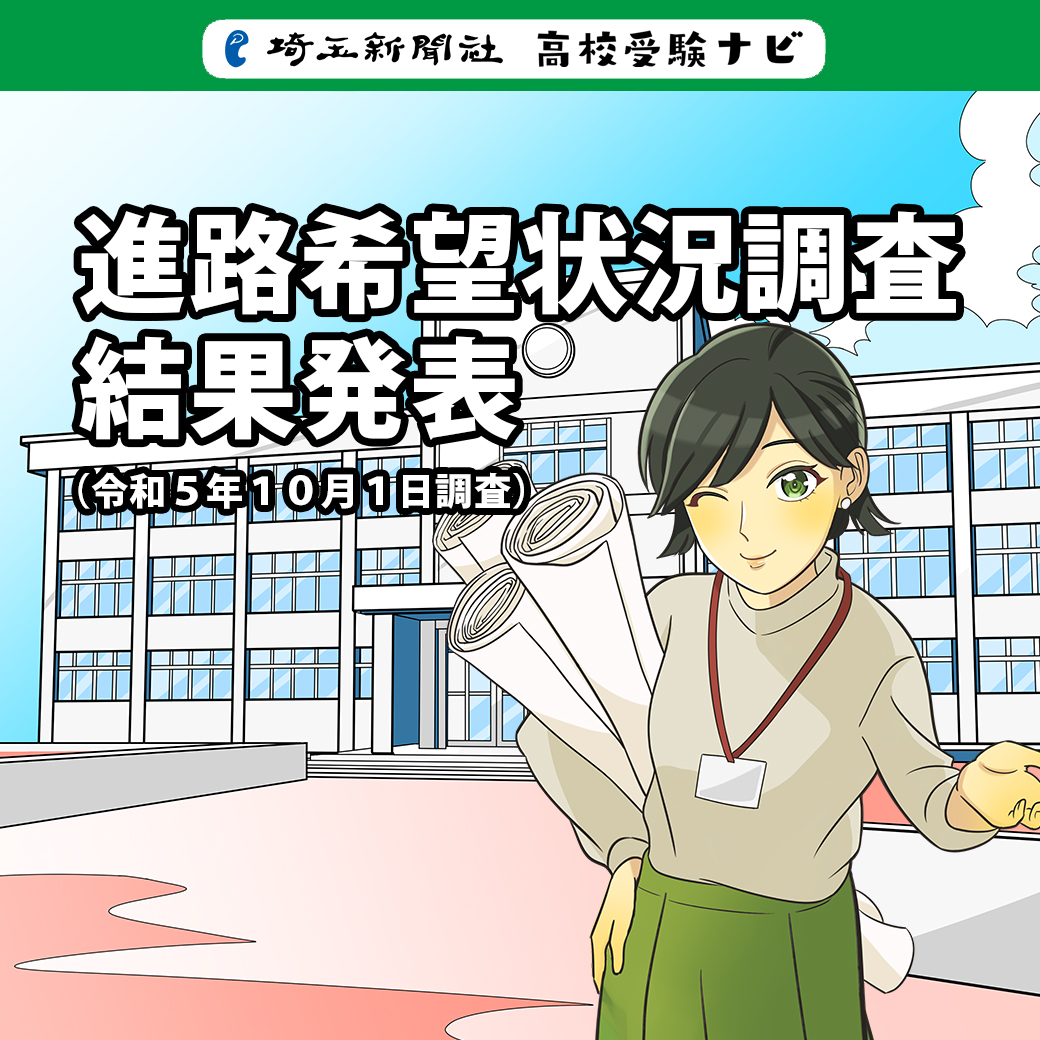アユ泳ぐ清流に歓声 伝統の地引き網漁/都幾川・高麗川
【都幾川】
「いろんな魚がいる。楽しい」。子どもたちが歓声を上げた。嵐山町の都幾川で10日、夏休みの家族が参加する地引き網漁「アユ漁体験と魚捕り」が開催された。時々雨がぱらつく曇天。川の流れも穏やかで、参加者らは自分たちで捕った魚をから揚げなどにして食べ、楽しんだ。

二瀬橋の下で地引き網を引く人たち。左端は金沢光さん=10日、嵐山町の都幾川
「県内にアユが泳ぐ清流を取り戻そう」と環境問題に取り組むNPO荒川流域ネット(鈴木勝行代表)が22年前から主催し、武蔵漁業協同組合、県西部漁業協同組合が協力している。7家族19人と同NPOのスタッフ30人らが力を合わせ、長さ約30㍍の網を川幅いっぱいに広げ、上流に引いた。
流れは濁りもなく浅く緩やか。水温も30度を超えず20度の少し上。子どもたちはNPOが用意したライフジャケットを着て、水中メガネを着け、水の中をのぞき、小さな網で魚を追いかけていた。
嵐山町立菅谷小学校2年生の野久保柊吏さん(7)は「2つ捕まえたよ」と岸辺の母に報告。兄の同小4年の柊馬さん(10)は浅瀬で上向きに寝そべって空を眺めて「いろんな魚がいっぱいいる。楽しい」。
捕れたのは体長15㌢のアユ1尾のほか、オイカワ、カワムツ、モツゴ、コイ、コクチバス、ウシガエル、カワリヌマエビなど多彩だった。
全体の指導は元埼玉県魚類研究会代表の金沢光さん(71)。金沢さんによると、この日のアユは、地元の武蔵漁業協同組合が5月に放流した神奈川産の養殖アユらしい。東京湾から荒川本流経由の天然アユの遡上(そじょう)は、川島町の魚道が機能不全のため期待できないという。
この日捕れた魚はから揚げにしてみんなで食べた。調理を担当したのはNPOスタッフで、日高市の広川千恵子さん(74)と鶴ケ島市の宮﨑弘子さん(79)。広川さんは「いつまでも、こういう魚が育つきれいな川にしておきたいね」。宮﨑さんは「高齢者のごみ出しや通院付き添いとか、普段はとても忙しい。この地引網が一番楽しい」。
NPOスタッフの中に高校生がいた。県立熊谷農高1年生の山田慎汰さん(16)と、県立妻沼高校1年生の井上諒一さん(15)。熊谷市立大幡中学校の同窓生で、熊谷のムサシトミヨ保護活動に参加。金沢さんからこの活動に誘われたという。鈴木代表らNPOの仲間は2人に「後継者に」と熱い期待を寄せる。
【高麗川】
家族連れ50人 アユ手づかみ
プリプリして元気!
日高市の高麗川で17日、伝統のアユ地引網漁が開催された。昔の清流復活を目指す市民団体のNPO荒川流域ネット(鈴木勝行代表)が主催し家族連れの市民50人とNPOスタッフ20人が参加した。川越市立芳野小学校4年の南島和歩さん(9)はアユを手づかみにして「プリプリしてすごい元気だ」と笑顔だった。

アユの地引網を引く子どもたち=17日、日高市の高麗川
水温は25度。水量は渇水状態で少ない。普段の半分以下という。NPOスタッフは「一雨ほしい」と空を見上げた。
青空で厳しい暑さとなったが、子どもたちは元気に地引網を引き、魚を追い、捕れた小魚の唐揚げを食べた。和歩さんの兄、同芳野中学校1年の創和さん(12)は「おいしい。少し甘い」。
熊谷市から高校生2人がスタッフとして参加した。県立妻沼高校1年生井上諒太さん(15)は「アユがいっぱい捕れて楽しい」。県立熊谷農高1年生の山田慎汰さん(16)は「初めて投げ網を教わった。オイカワが1尾捕れた」。
にぎやかな水辺を横目に、木陰で炭火でアユ100尾の塩焼きに懸命だった男性2人は、午前9時から1時間も煙と格闘した。城西大学の元教授、松本明世さん(72)と教授の真野博さん(58)。「僕らは食の専門家だからね」と松本さん。「好きでやってる」と真野さん。
2人とも食品栄養学が専門。「コラーゲンが豊富で骨や皮や内臓も。全部食べられるのはアユだけ。丸ごと全部食べてね」と勧めていた。和歩さんらの母美奈さん(47)は「皮はパリパリ、中はしっとり。絶妙な焼き方」と絶賛。
地引網の収穫は15㌢から17㌢級のアユ7尾のほか、オイカワ、カワムツ、カジカなど魚類のほか、カワニナ、スジエビ、カワリヌマエビ、スッポン、ウシガエルのオタマジャクシなど。
地引網を指導した県魚類研究会の代表、金沢光さん(72)は「カジカがいたことはこの川が清流で、良好な環境だという証拠」。
金沢さんの解説を白板に書き写したスタッフ、ときがわ町で里山の自然保護に取り組む山本美穂さん(67)は「皆さんが楽しそうでうれしい」。はるばる戸田市からスタッフとして参加した会社員長谷川理さん(45)は「戸田にもこんな清流が欲しい」と話した。
=埼玉新聞2025年8月15日付け8面/20日付け11面掲載=
サイト内の
熊谷農業高校の基本情報は→こちら
妻沼高校の基本情報は→こちら
カテゴリー
よく読まれている記事