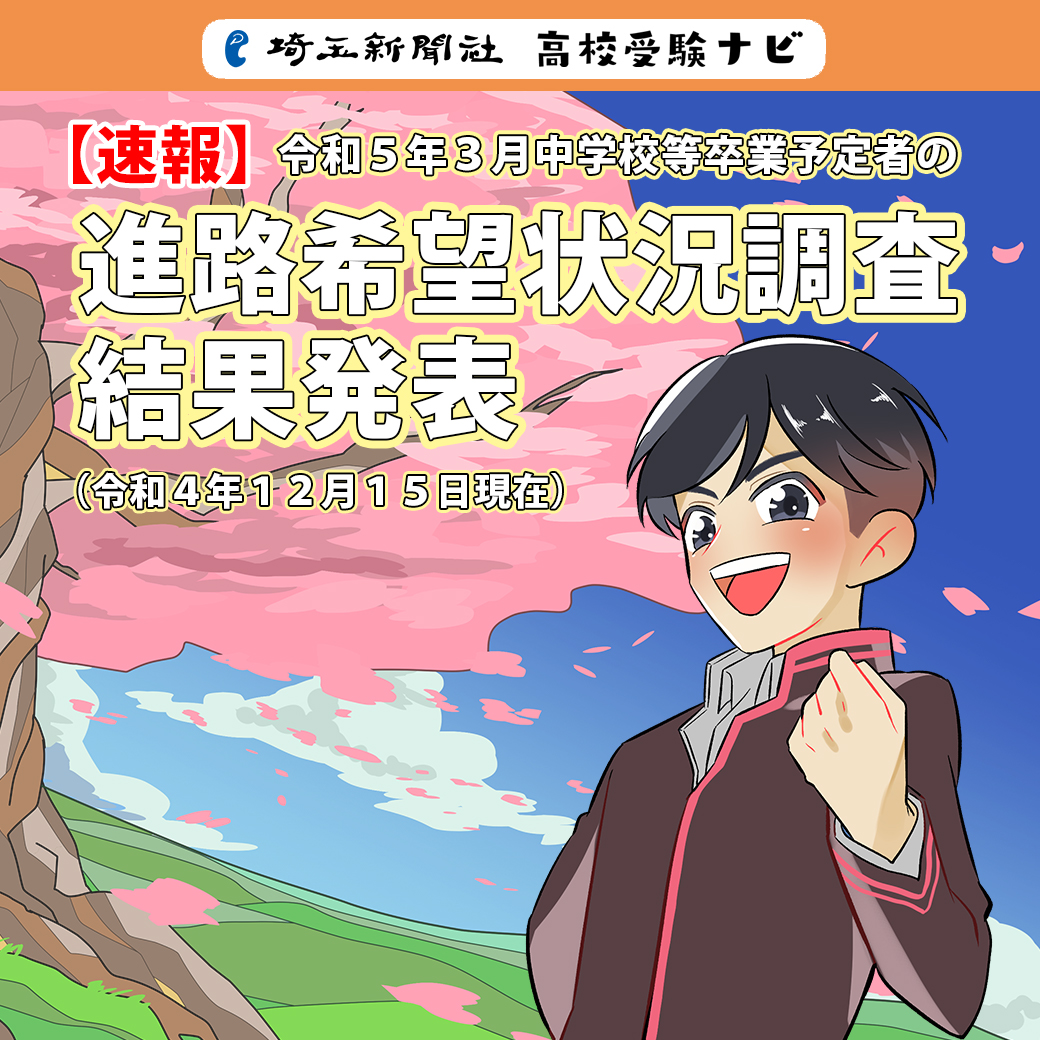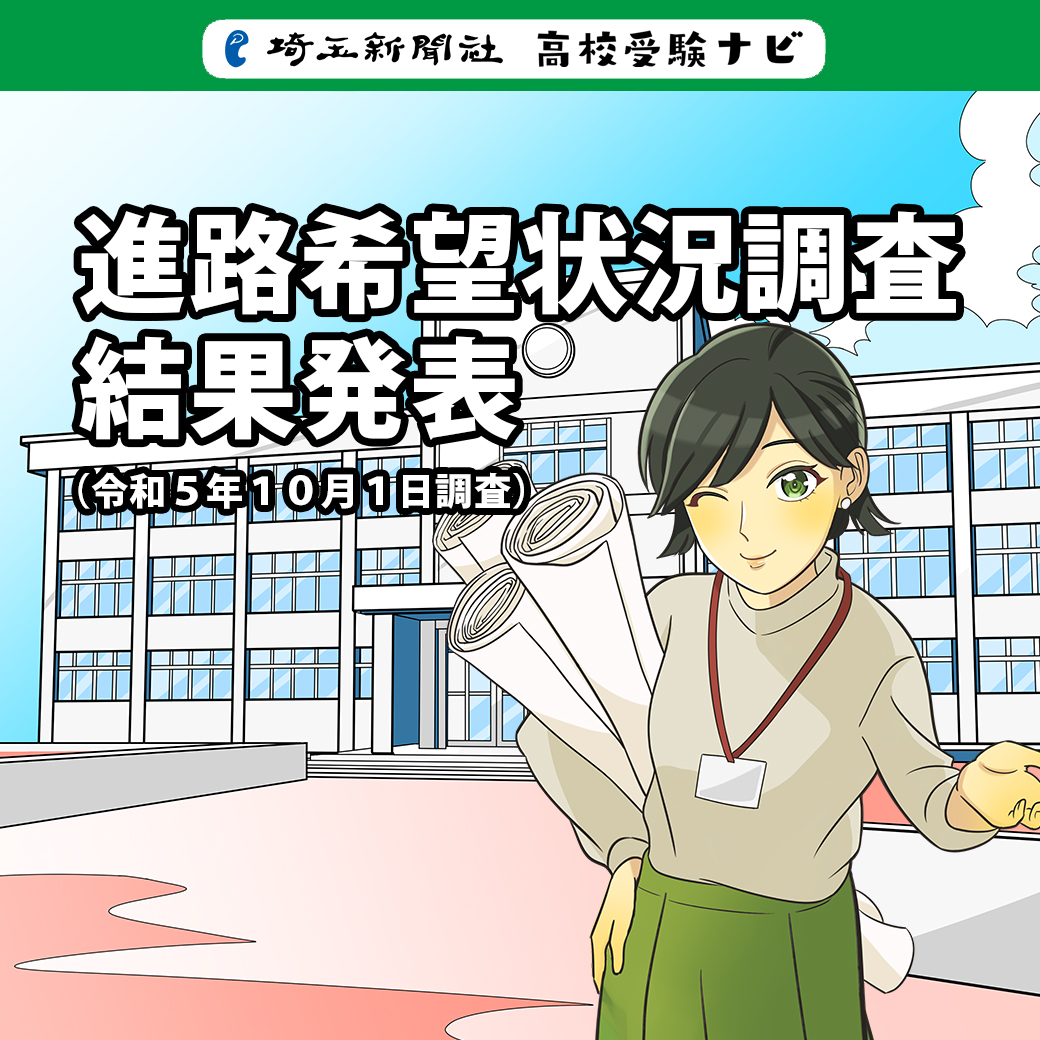修学旅行前の平和学習で大学生、市民の会代表が講演ー熊谷高校
県立熊谷高校(市川京校長)は10月27日、熊谷市大原の同校で2年生の修学旅行を控えた平和学習を実施し、「熊谷空襲を忘れない市民の会」代表の米田主美さん(80)や熊谷空襲を題材に映像制作を行っている大学生らが講師として招かれた。生徒は太平洋戦争終戦前夜の1945年8月14日から翌15日未明にかけて、市街地が甚大な被害を被った地元の戦禍について知ることで、若い世代が継承する重要性を学んだ。

パネルディスカッションで語る登壇者たち=10月27日、熊谷市大原の県立熊谷高校
同校は毎年、修学旅行の初日に広島市を訪問。広島平和記念資料館を見学するなどして、広島の原爆について考えている。今年は今月25日から29日まで、修学旅行を実施。例年は事前学習として、県内の被爆者の証言を聞いていたが、今回は熊谷空襲を取り上げることになった。企画を担当した宮嶋敏教諭(60)は「今年は戦後80年なので、市内の戦災を知ってほしかった。熊谷空襲については、高校生と近い世代の若者たちの活動が動き始めている。生徒にとっても、インパクトがあるだろうと思った」と言う。
在籍する2年生318人は7月、市立熊谷図書館の学芸員を招いた講演で、熊谷空襲の全体像を把握。夏休みには、各自が市内で開かれた関連展示や戦跡巡りなどを行い、リポートにまとめて提出した。2回目の講演会は、事前学習の締めくくりとなる。
熊谷空襲の日に生まれ、市内の自宅が全焼した米田さんは、軍人だった父親が終戦5カ月前に戦死したことなど、自身の人生を語った。米田さんは「私は父のぬくもりも知らない。それが戦争」と非情さを強調する。ドキュメンタリー映像を作った日本大学2年生の小林尚平さん(21)、証言などを収めた映像の制作を進める目白大学4年生の松田みなみさん(22)、戦跡マップを完成させたグループの現リーダーで立正大学大学院博士後期課程1年生の本多一貴さん(24)も、それぞれの活動について紹介した。
パネルディスカッションでは、登壇者らが意見交換した。松田さんは「映像で記録すれば、後世まで教訓を伝えられる。それを若者の視点で考え、作ってみたかった」と説明する。小林さんは「世代を重ねると、体験者のような迫力は薄まっていく。でも、事実として残せば、戦争が再び起きそうになった時に踏みとどまる力となるかもしれない」と期待。本多さんは「戦争や平和について、少しでも考え行動してみることが大切。それは将来、自分たちで解決しなければいけないあらゆる社会問題に向き合う場合に役立つ」と投げかけた。
米田さんはロシアのウクライナ侵攻などを例に挙げ、「戦争は始めてしまうと、停戦することすら難しい。記憶や教訓の風化は恐ろしいこと。たくさんの若い人たちに熊谷空襲の事実を知ってもらえ、とてもうれしい」と継承を願う。
修学旅行実行委員長の市原優広さん(17)は「入学する前は熊谷空襲の存在すら知らなかったが、考えるきっかけになった。修学旅行で学びを深め、教訓を後世に残さなければ」と誓った。
=埼玉新聞2025年11月6日付け15面掲載=
サイト内の熊谷高校の基本情報は→こちら
学校の特徴~学校からのメッセージ2025~
「質実剛健」「文武両道」「自由と自治」の精神を受け継いで130年、3万を超える卒業生は様々な分野で日本や世界のリーダーとして活躍。学力向上、進路希望の実現は言うに及ばず、先行き不透明な時代をたくましく生き抜くために不可欠な「人間力」の育成を目指す。活発な部活動、伝統ある学校行事を通して、心身ともに強靭でしなやかな生徒を育む。熊高ならではの彩り豊かな高校生活には、一生ものの友との出会いが待っている。
カテゴリー
よく読まれている記事