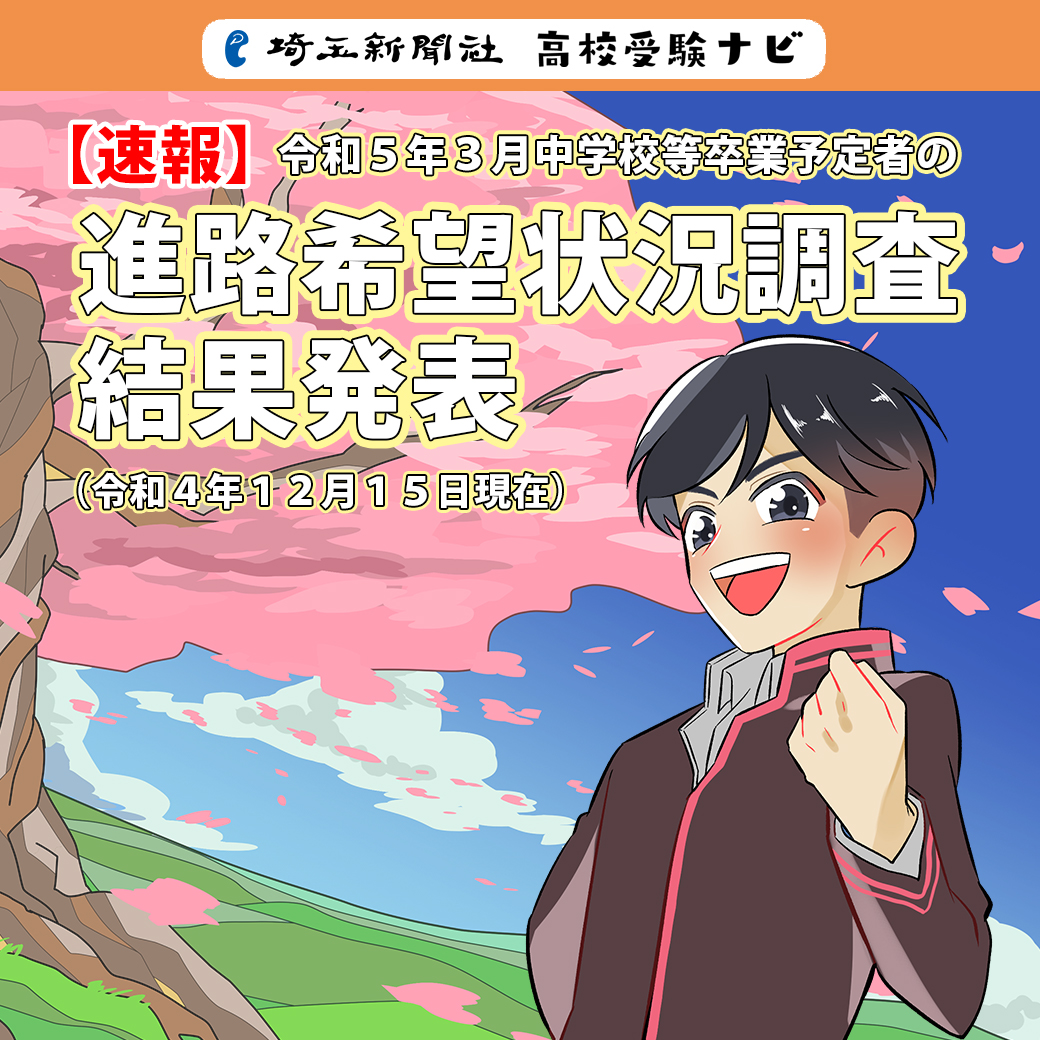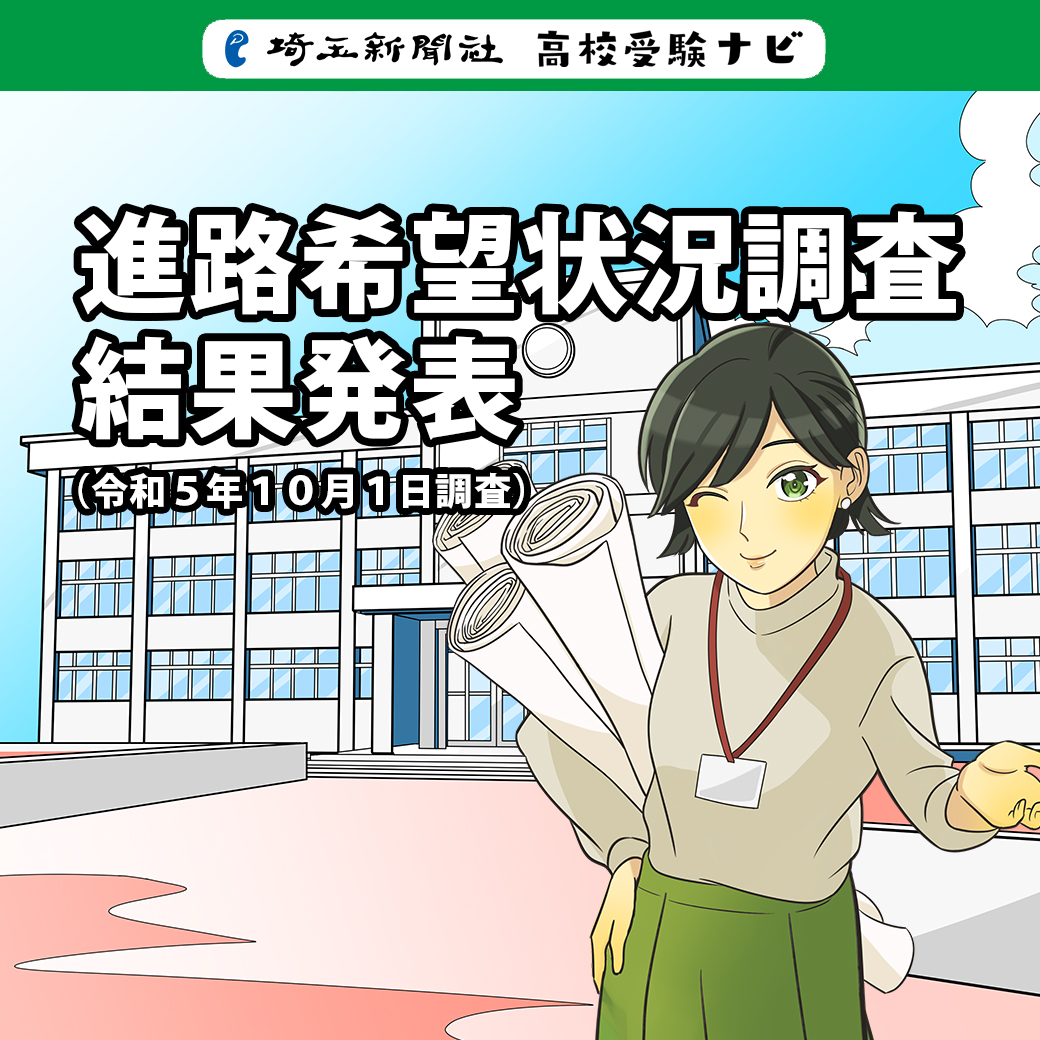所沢北高校生物部が小学生に講座 外来害虫から桜を守ろう

高校生が小学生に標本の作り方を教えた=18日、所沢市並木
外来害虫「クビアカツヤカミキリ」による食害から桜の木を救うため、県立所沢北高校生物部の生徒が18日、同校で市内の小学生向けに講座を開催した。小学生は実際のクビアカツヤカミキリを使った標本作りにも挑戦。高校生は「周りの人や家族にも伝えて、埼玉県や日本の桜を守っていきましょう」と呼びかけた。

クビアカツヤカミキリのオス(左)とメスの標本
クビアカツヤカミキリは、特定外来生物に指定される中国原産のカミキリムシ。幼虫が桜や梅などのバラ科樹木を摂食し、木が枯死する被害が発生しており、早期発見や防除が必要。県内では2013年に草加市で初めて被害が確認された。所沢市内ではまだ確認されていないが、県北部から南下するように被害地域が拡大しており、いつ市内に侵入してもおかしくない状況だという。
講座では「サクラを守れ!クビアカ退治大作戦」と題したクイズ形式で、分かりやすくクビアカツヤカミキリの生態などについて解説。木くずが混じった排出物「フラス」によって、幼虫が侵入した木を見分けることや、成虫のメスは最大千個の卵を生むことなどを小学生が学んだ。
標本作りでは、小学生が生徒の指導を受けながら、湯に浸けて柔らかくしたクビアカツヤカミキリの触角や足を作りたい形に針で留め、固定した。小学生は実物を観察し、夢中で針を刺していた。標本は持ち帰って約2週間乾燥させ、各自でピンを外してラベルを貼る。
講座は同日に2回開催され、午前の回では小学生15人が参加した。学校の授業で外来種について勉強し、興味を持ったという伊藤小春さん(11)は、「かわいそうだけれど、(樹木を)食べてしまうのは大変なので捕まえないといけないと分かった。(標本作りは)本物の口などを見ることができて楽しかった」と話した。
生物部の現在の部員は9人。同部では21年からクビアカツヤカミキリについて研究し、県内の被害拡大距離が1年で約11㌔であることなど調査した。「所沢北式防除策」として、割れ目が少なく産卵しにくい若い桜に植え替えることを提案している。研究を社会に還元させようと、今回の講座を初めて実施した。
生徒は、「放置していたら、桜並木もすぐになくなってしまうかもしれない。周りの人や家族にも伝えて、埼玉県や日本の桜を守っていきましょう」と小学生に呼びかけた。部長の広瀬真武(まなむ)さん(17)は「日本の桜文化を守ることに一役買えればうれしい」と期待した。
=埼玉新聞 2025年8月24日付け11面掲載=
サイト内の所沢北高校の基本情報は→こちら
学校の特徴~学校からのメッセージ2025~
本校は、昭和49年に開校し、今年で 52年目を迎えました。「文武両道」を目指し、学習活動とともに部活動・学校行事にも熱心に取り組んでいます。授業は 65分授業で、毎日 5時間、週当たり 34時間に相当する授業( 50分授業に換算)を行っています。国際交流事業としてニュージーランド研修等を実施しており、令和 6年度から SSH指定校となりました。文系理系の選択に関わらず、科学的な見方や考え方、探究的に学ぶ力を高める教育活動を行っています。
カテゴリー
よく読まれている記事