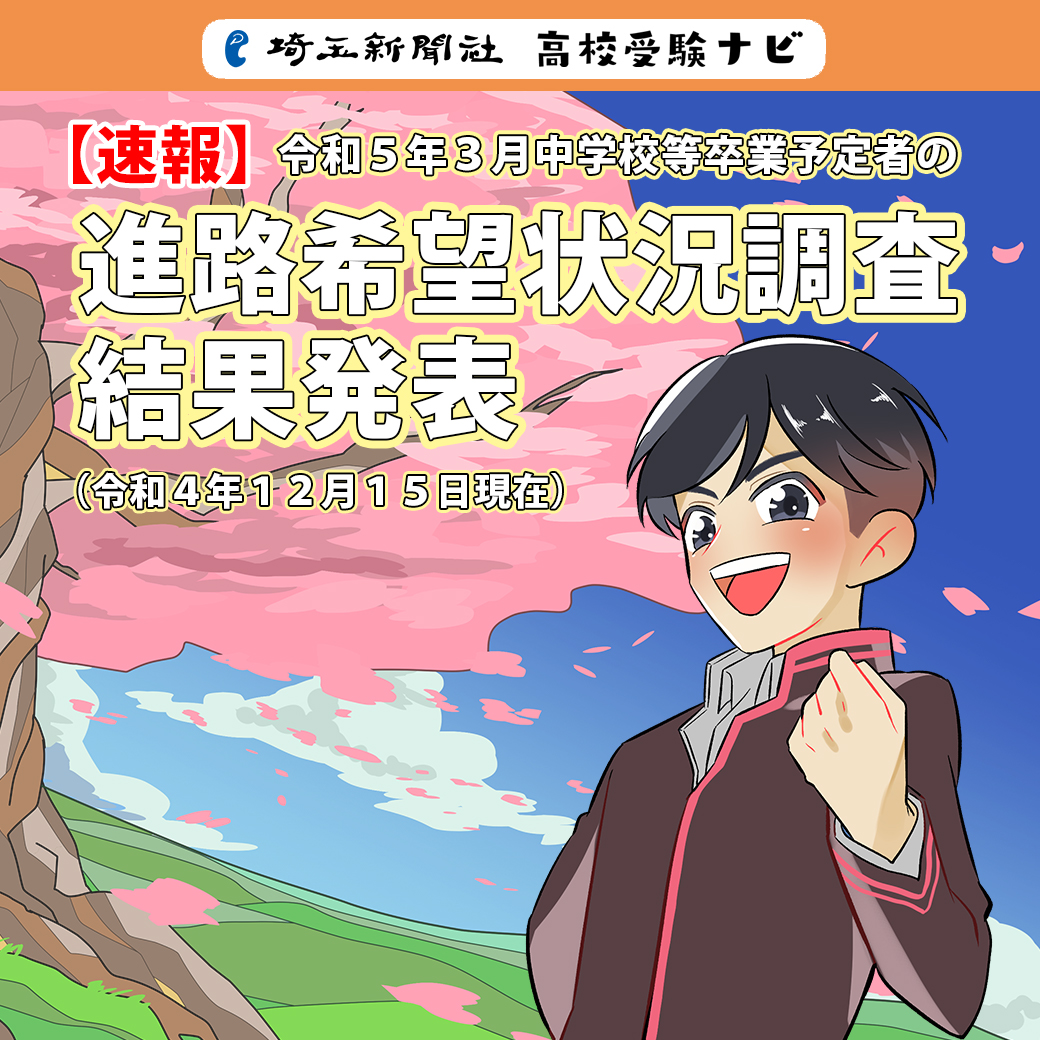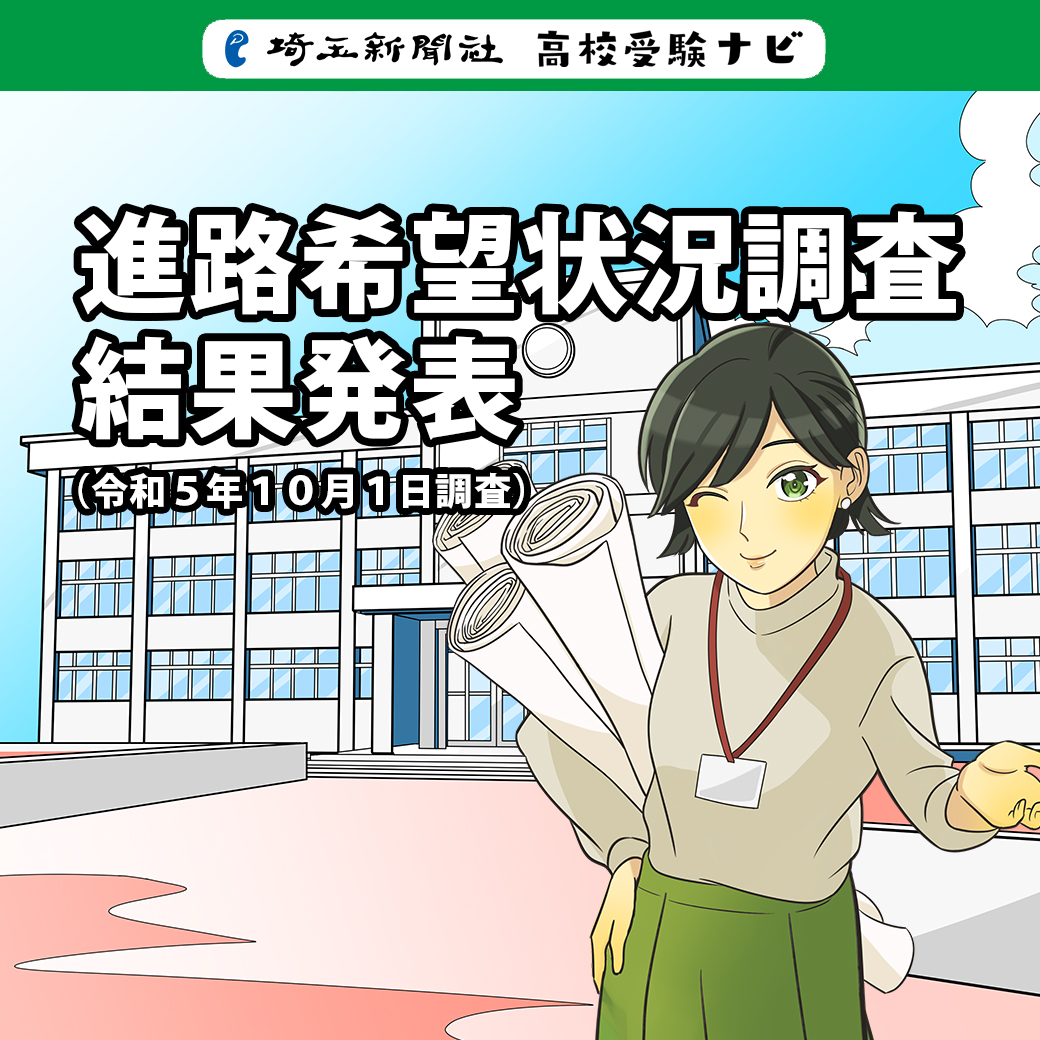東洋大学理工学部と水質研究ー杉戸高校理科部
杉戸町清地の県立杉戸高校理科部は通学路途中にある大落古利根川の水質調査を行っている。研究は4月で3年目。昨年から東洋大学と共同研究も始まった。部員らはなじみある川を大切にしようと、研究を重ねている。

東洋大教授らとフィールドワークを行い採水と採泥を行った県立杉戸高校理科部員ら。マイクロプラスチック問題の研究にも取り組む=3月27日午前、杉戸町
■通学路の川
顧問の松下裕也教諭がきっかけ。2022年4月に同校に赴任。翌23年、顧問になった時に身近な題材をテーマに「みんなが何かしらで関わっていることに着眼点を置ければ」と考えた。部長の鈴木利奈さん(17)も「一緒に登校している友達と昨日雨が降ったから水の量が多いね、と話題になる川」という。
松下教諭は同校で化学を担当。だが川の水質調査は「経験のない分野」で県環境科学国際センターへ協力を求め、指導を仰いだ。採水する資機材もなく活動一年目は「掃除用のバケツにひもをくくりつけて採水した」。月1回採水し簡易検査キットで分析した。
データに取ってまとめ、川に関心のある人が一堂に会して活動内容の発表や情報交換を行う「川の再生交流会」などにも参加。同センター木持謙氏の紹介で同大学理工学部の山崎宏史教授と出会い、24年夏からは共同研究も始まり、11月には同学部と高大連携に関する協定を結んだ。
■川を大切に
共同研究は長期休み期間中の2日間を使って活動。1日目は教授らと採水などを行い、2日目は同大学で分析などを行う。理科部の中野純也さん(16)は「大学の先生と一緒に研究できる機会は珍しい」、菅原貴琉さん(16)も「自分だと見つけられない発見がある」と意欲を見せる。
研究では採水前に川の水や生き物、景色などを観察し記録をつける。自分たちの感覚的な評価と物理化学的な評価を突き合わせることで理解を深めている。
同研究に携わる同大総合情報学部の大塚佳臣教授は「人にはいろいろな自然の見え方がある。みんなが何で違うように見えるのか、お互いに認識し合うことで多様な物の見方を学んでもらえたら」と話す。山崎教授も「高校生の多様な視点を期待している。将来、水環境を大事にする意識が醸成していくと良いと思っている」と述べる。
理科部の金子裕希さん(16)も「季節によって汚れが違う。川が一年中きれいになっていけば」、橋本凌一さん(16)も「普段集中して川を見る人は少ないと思う。川に注目して大切さを分かってほしい」と話し、これからも活動を続けていく。
=埼玉新聞2025年4月8日付け10面掲載=
サイト内の杉戸高校の基本情報は→こちら
学校の特徴~学校からのメッセージ2024~
【躍動・敬愛・誠心】の校訓のもと、新しい取り組みを続ける。授業は55分カセット方式で、土曜授業なしで週33単位を確保。教育課程は大学受験対応。入学直後に2日間行う「スタートアッププログラム」で、高校の深い学びへの意識改革を実施。特に2日目の「英語しか使えない杉戸高校」は、世界各国より外国人講師40名以上を集め、異文化理解とコミュニケーション能力の向上で人気。SDGs探求も奥が深く、楽しい。令和7年度入学生からは、生徒会役員が長年かけてデザインした新制服となりますので、ご期待ください。
カテゴリー
よく読まれている記事